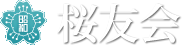座談会『初等部:歩んできた70年を振り返り、これからの未来を語る』
| 開催日時 | 2024年09月29日 日曜日 13:00-13:30 |
|---|---|
| 会場 | 昭和女子大学本部棟3階ホール 桜友会総会懇親会場 |
| 登壇者 | 岡野栄之(13回生) 桜友会新会長(第5代) 慶應義塾大学教授 再生医療リサーチセンター長 前田崇司 昭和女子大学附属昭和小学校校長 平原史樹(6回生) 桜友会前会長(第4代) 横浜市立大学名誉教授(司会) |
はじめに
- 平原
- 初等部創立70年を数える歴史のなかで同窓会の桜友会は1964年に創立されました。
本日は2024年の桜友会総会を迎え、会場には第2代の桜友会会長川上龍美さんが、さらに2006年から現在のスタイルの桜友会活動が開始されましたがその折の立役者である第3代桜友会会長中田彰生さんもお越しです(ご両人それぞれに紹介され、参会者へ立礼)。
この座談会の司会を務めます平原史樹が第4代、さらに先ほど総会で承認いただきました新たな第4代岡野栄之会長と本日は歴代4名の全会長が出席しております。また長年にわたりご尽力、ご活躍いただいた歴代の桜友会役員のみなさまの名簿、また桜友会の略史の記録については桜友会のホームページで現在ご披露しております。また今般、川上初代会長から寄稿があり、懐かしい貴重な写真とともにおそらく卒業生一桁世代には「そうだ、そうだ」とおもわず膝を打ってしまうような懐かしいエピソードが桜友会ホームページに掲載されております。ぜひご一読をお勧めします。
さて本日の座談会では長年培われた伝統の中で現在、先駆的な教育実践を展開しつつある昭和小学校の前田校長、新会長の岡野栄之さんとともに大いに語っていただこうと企画しました。まずはそれぞれにひとこと、自己紹介をお願いします。
自己紹介
- 岡野
- 今般、総会でご承認いただき会長に就任しました13回生の岡野です。2年前から昭和女子大学(学園)の評議員もしておりますが 現在、ボストンのMIT(マサチューセッツ工科大学)でも研究を進めており、昭和ボストンにも赴いて(宿泊もさせていただきながら)初等部の生徒さんにもお話したりしております。いまや昭和では学校をめぐる新たな展開が急速に進化していることなど、ぜひ卒業生として盛り上げていききたいと思います。
- 前田
- 私は小学校の教員から始まり、校長職等を経たのち、2022年に本校に着任しました。今までも子どもたちの成長にかかわり、自分も成長できるこの仕事にやりがいを感じて奉職してまいりました。学校は人が集い、つながっていくところ。昭和の大切にしていることは“世の光となろう”という建学の精神です。人見先生の教えをもとに、初等部では、人のぬくもり、思いやりを大切にして、人格として潤いのある人に育てるという考えが貫かれているところが素晴らしいと思っております。
また、基礎学習を大切にしてそれを総合的に広げる学びをもって社会に出ていく、基礎学習、総合学習の大切さも継続してきました。さらに、本校には歴代の先達の皆様はじめ、大変すぐれた先生方が歴史を刻んでこられました。これからも先輩方の思いを胸に歩みを進めていけたらと思っています。
- 平原
- 皆様のお手許には桜友会の歴史の概略が資料として差し込んでありますが(ホームぺージに略史、歴代役員名簿は載っています)それを参考にしながら岡野新会長には育ったころを振り返っていただき、前田先生には昭和小学校の歴史を振り返ってお話をお願いします。
育ったころ、歴史をふりかえって
- 岡野
- 私が初等部で学び、卒業したのが1971年。臨海学校でも脱落しそうになると今では許されないような強烈な叱咤の声が人見先生から飛んでくるような風景でしたね(笑)。自分としては、根性がついて大変感謝しましたが・・・。いま、初等部では新たなコース課程ができて素晴らしいことと思います。自分自身を振り返ると、総合学習はとてもためになりました。自分で考えて何が大切かを考え、鍛えていく。AIが進化してもそれに勝る力を鍛えられたと思います。
- 平原
- 学校での現場のご苦労、お考えなどはいかがですか?
- 前田
- (スライド呈示) こちらは初等部の紹介用のスライドなのですが、「古人の求めしところを求めよ」の通り、先達が何を目指し求めていたのかを常に大切にしたいと考えています。予測不可能な変化の激しい時代を迎えています。子どもたちはそうした未来社会に巣立っていくわけですから、自分のよさや可能性を信じ、あらゆる他と協働しながら共に新たな価値をつくり、社会に貢献できる人として育っていってほしいと考えています。その意味で、初等部の3つの目標をもとに、育むべき資質・能力として「Lead yourself~自分リーダーシップの発揮~」を掲げ、教育理念の根幹を引き継いでいます。
今春、新たに開設しました2つのコース(探究コース、国際コース)ですが、探究コースでは 『体験から学び、言葉との往還から好奇心や探究心をはぐくむ』実践を展開しています。例えば一年生「昭和っ子の研究」の生き物探究では、徹底して「材」である動物や昆虫に関わり、「問い」を立てて夢中になりながら学び、友だちと共に高まり合ってさらに自身の「問い」を深めていく姿が見られています。
一方で、これまで大切にされてきた学寮での学びや異学年での交流も大切にしています。昭和の学寮での学びは、いわゆる非認知能力も高める大切な機会となっています。夏の「海の学校」は残念ながら猛暑で気温が高く、これまでの内容での実施が困難となりましたが、春に季節を変えての望秀での学びは継続しています。
- 平原
- 昭和の学園全体をみるとグローバル化が進み、昭和ボストン、テンプル大学、ブリティッシュスクール・イン・トウキョウ昭和などキャンパスは見た目にも大変国際的になっています。学園の昭和女子大学評議員会には桜友会メンバーから太田鈴子(3回生)、吉田昌史(6回生)、平原史樹(6回生)、岡野栄之(13回生)の各氏が参加して学園の大きな進化、変化をみまもっています。学園の国際化、そのなかでの初等部の在り方を考えてみるといかがでしょうか。またAI,ギガスクール、データサイエンスなど情報近代化の時代に初等部はどうなっていくのかなど、お聞かせください。
新たな潮流の中での昭和
- 岡野
- 生物進化の中でも環境変化に順応し、対応できた存在だけが生き残ります。学校についても同じ事が言えます。 昭和の選択は機敏でとてもよいと思います。初等部の国際化については、卒業後の教育体制をどう継続、担保していくかが大事と思います。いまやZ世代では想定外の能力を実装、実践しているので、ぜひそのような人材を育ててほしいものです。
- 前田
- 国際化の波は留まることはないと思います。その意味で、世界との対話は必須となると考えます。また、少子化は続き、直近の令和5年の出生数は70万人台となっています。これからを考えると昭和の100周年記念を迎える2050年ごろにはわが国の人口全体も大きく減少すると言われています。そういった意味でも、初等部は変化に鋭敏に積極果敢なチャレンジをすすめ、選ばれ続ける学校でありたいと考えています。そして、国際化と言えば、初等部5、6年生の希望者が昭和ボストンに学びに行っていますが 10-11日間のフレンズとのかかわりでは、自分の伝えたい思いがなかなか伝わらない中、もっと英語を勉強したい、自在なものにしたいといった切実な思いをもって帰ってきます。こうした主体的な学びの環境を整えていくことも大切にしたいと思っています。
今回開設した小学校の「国際コース」ですが、コンセプトは、グローバル社会で活躍できる世界標準の力の育成です。国語や社会等は第一言語である日本語で学びますが、他の教科等は内容について学習指導要領準拠の本校教育課程で学びますが、すべて英語で学ぶ「英語イマージョン教育」です。幸い義務教育を担う一条校の小学校として全国で初めて「ケンブリッジ・インターナショナル」の認定校になることがきました。36名の一クラスですが、年間およそ1000時間の授業のうち、600時間以上を英語で学ぶことになります。また卒業の出口戦略では、現在昭和中・高の真下峯子校長ともいろいろな相談、検討を進めているところです。
- 平原
- 30分の座談会との制限もあるので、少し物足りないですが、桜友会の目指すべきこと、希望していることをさいごにまとめていただけますか。
まとめ
- 岡野
- 同窓会は母校を支援する組織です。総会でも話の出てきた寄付は健全に卒後にお願いしていくのはよいのではないかと思います。自身が研究の場として働く米国のMIT(マサチューセッツ工科大学)は大いなる寄付制度で大きな発展をしています。本校のOB、OGにはぜひ知っていただき、学校を発展させるために皆で支えていきたく思います。新たな国際コースへの期待も含めて、これから優れた大学のロールモデルとして発展してほしいと思います。
- 前田
- 新会長からの心強いお言葉もありがとうございます。本校では“校長道徳”の時間があり、子どもたちにもたくさんのメッセージを送っています。昭和っ子の子ども達にはこれからも伝統を大切にして、新たなチャレンジで様々な課題を乗り越えていってほしいと思っています。国際コースには、本校卒業生で世界的に有名なシルクドソレイユで活躍された卒業生の能登原あいさんに体操の授業をもっていただいています。また、同じ関心等でつながり、探究的に楽しむ“乗り物クラブ”の活動では、JTBにいる卒業生が山梨のリニアモーターカーの見学等をアレンジしてくれました。ぜひ、卒業生のつながりのもと、皆様のお力添えをこれからもいただければと思います。
- 平原
- 本日はお二人の話からも母校の熱い息吹が感じられたと思いますが、われわれもぜひサポーターとして精いっぱい母校を支えていきましょう。本日はありがとうございました。